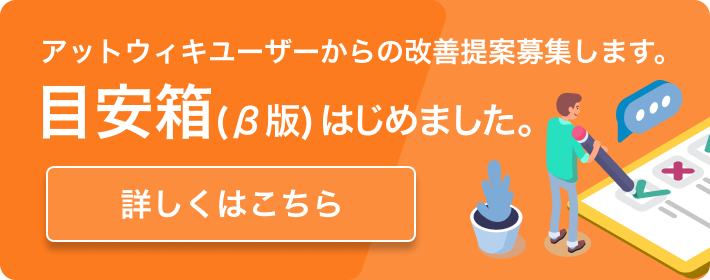「夏祭りに連れて行けよ。」
真夜中の着信に寝ぼけながら電話をとると、相手は突然そう言った。
「…急になんですか?」
「夏祭りの季節だろ?だから。」
「でも…」
「明日の夕方からなら空いてるからさ。浴衣着てこいよ。」
かかってきた時と同じように、電話は突然切れた。
そう言えば、明日から地元で夏祭りがあるんだった。
そんなこと、話したことすら忘れていた。
そう言えば、明日から地元で夏祭りがあるんだった。
そんなこと、話したことすら忘れていた。
「お祭りって…大丈夫なわけ?別にいいけど…。」
翌日、久しぶりに実家に帰り、大騒ぎで浴衣を着付ける。
もちろん自分では着れないので、母の手を借りる。
もちろん自分では着れないので、母の手を借りる。
浴衣の仕上がりよりも、彼がこんな所まで本当に来るのかが気になる。
着つけながら、母は執拗に誰と出かけるのかと聞いてきたけど、言えるわけない。
髪をゆるくアップにして、小さなピアスを耳に飾る。
慣れない下駄を鳴らして、待ち合わせの場所まで急ぐ。
すでに足が痛いけど、待たせるわけにはいかない。
着つけながら、母は執拗に誰と出かけるのかと聞いてきたけど、言えるわけない。
髪をゆるくアップにして、小さなピアスを耳に飾る。
慣れない下駄を鳴らして、待ち合わせの場所まで急ぐ。
すでに足が痛いけど、待たせるわけにはいかない。
******************
案の定、思いっきり目立っている。
ただでさえ佐藤浩市なのに、それがご丁寧に浴衣なんて着こんでいるせいで色んなものがダダもれだ。
周りでひそひそやってる人達は、ロケで女優でも待ってるとでも思っているんだろう。
声をかけるのに戸惑っていると、向こうが先に振り向いた。
ただでさえ佐藤浩市なのに、それがご丁寧に浴衣なんて着こんでいるせいで色んなものがダダもれだ。
周りでひそひそやってる人達は、ロケで女優でも待ってるとでも思っているんだろう。
声をかけるのに戸惑っていると、向こうが先に振り向いた。
「おう。」
私をみつけると、浩市は軽く笑って手を挙げた。
周囲の視線が一斉に私に向く。ああなんかもう、本当にすみません。
周囲の視線が一斉に私に向く。ああなんかもう、本当にすみません。
「おせーよ。」
「ごめんなさい。…なんかすごい見られてるし、早く行きましょう。」
足早に歩き出そうとする私の手を取って立ち止まらせると、上から下まで眺めて浩市は言った。
「思った通り、浴衣似合うな。(ニヤリ」
それはこっちの台詞だと思った。
濃紺の地に古典柄の入った浴衣に、ベージュの角帯。控え目な柄が、中年男の色気を際立たせている。
少し広めに開いた胸元に思わず目が行ってしまう。
濃紺の地に古典柄の入った浴衣に、ベージュの角帯。控え目な柄が、中年男の色気を際立たせている。
少し広めに開いた胸元に思わず目が行ってしまう。
「私、おっさんみたい。」
小さくつぶやいて、歩き出す。お祭りのある神社まではすぐだ。
小さな私の遊び場だった、小さな神社。そこにこの人を連れて来るなんて。
小さな私の遊び場だった、小さな神社。そこにこの人を連れて来るなんて。
******************
「祭の出店っていいよなあ。」
こんな田舎じゃ、彼に話しかけてくるような人はいない。
ちらちらと飛んでくる好奇の視線に気づいているのかいないのか、当の本人はいたってのんきなものだ。
出店の黄色い明りに照らされた彼の顔は初めて見るような顔で、なんだか照れくさい。
ちらちらと飛んでくる好奇の視線に気づいているのかいないのか、当の本人はいたってのんきなものだ。
出店の黄色い明りに照らされた彼の顔は初めて見るような顔で、なんだか照れくさい。
「金魚すくいやりたい。」
浴衣の袖をひかれて振り返ると、彼の目は浅い水槽に泳ぐ金魚にくぎ付けになっていた。
「無理ですよ、連れて帰れないでしょ?」
どっちが大人なんだかと思いながら、軽く諭す。
踵を返そうとすると、しゃがみ込んだ浩市に引っ張られ、隣にしゃがんでしまう。
踵を返そうとすると、しゃがみ込んだ浩市に引っ張られ、隣にしゃがんでしまう。
「この金魚が欲しいなって思ってさ。」
「これ?普通の金魚じゃないですか。なんで欲しいの?」
「だって、お前に似てない?この金魚。(ニヤリ」
…もう帰りたい。
******************
神社では、地元の子供たちの神楽が披露されている。
子供たちのつたない踊りに皆が目を細める背後を歩いて、神殿にお参りをする。
叶う事のない願い事を唱えて、そっと横を覗き見る。
浩市はまだ目を閉じて、なにやら真剣にお参りをしている。
私の視線に気づくと、ちょっと照れたように口元をゆるめた。
子供たちのつたない踊りに皆が目を細める背後を歩いて、神殿にお参りをする。
叶う事のない願い事を唱えて、そっと横を覗き見る。
浩市はまだ目を閉じて、なにやら真剣にお参りをしている。
私の視線に気づくと、ちょっと照れたように口元をゆるめた。
「何をお願いしたんですか?」
「秘密。」
「ドラマの視聴率なんとか~とか?」
「そんなことどうでもいいよ。」
「…ちょっとくらい教えてよ。」
「聞きたいの?」
「はい。」
「さっきの金魚が欲しい…ってね。(ニヤリ」
「金魚?まだそんなこと言って…」
言い返そうとした途中で、顔が熱くなった。きっと、耳まで赤くなってるんだろう。
私の反応に、浩市は満足げに唇の端を上げた。
こうやって、この人はいつも私をからかう。
私の反応に、浩市は満足げに唇の端を上げた。
こうやって、この人はいつも私をからかう。
「あ、あの…あっちの方に行ってみませんか?」
頭を冷やそうと、神殿の裏へ浩市を案内する。
ここは小さかった私の秘密の場所。しめ縄のかかった大きな御神木と、大きな岩がある。
ここは小さかった私の秘密の場所。しめ縄のかかった大きな御神木と、大きな岩がある。
「子供の頃、ここが秘密基地だったんです。」
誰もが知っている場所なのに、私が来る時はいつも誰もいなくて、ひっそりひんやりとしていた。
「秘密基地か…いい響きだな。」
浩市は大きく深呼吸をすると、夜空にそびえる大きな木をじっと見上げた。
「たまにはこういうのもいいな。」
振りかえって笑うと、浩市は私の先に立って歩き出した。
「でっけー岩。こういうの、『ご神体』っていうのかな?」
「しめ縄がかかってるのは、全部神様ですよ。」
「それならここ、神様だらけだな。ま、神社ってのはそんなもんか。」
「…そんなもんですよ。」
足が痛い。下駄なんて、慣れてないのだ。
待ち合わせに向かう途中で走ったのと、玉砂利の上を歩いたせいで鼻緒がこすれて皮が剥けてきている。
できることなら、今すぐ裸足になりたい。
待ち合わせに向かう途中で走ったのと、玉砂利の上を歩いたせいで鼻緒がこすれて皮が剥けてきている。
できることなら、今すぐ裸足になりたい。
「どーしたー?」
足の事ばかり考えていたのが、声をかけられて我に返る。
「ちょっと足、痛くて…でも、大丈夫。」
「足?下駄にやられたか。ちょっと見せて。」
「いや、大丈夫ですって。」
「いいから見せろって。」
足を取ろうとした手を避けて、体のバランスが崩れる。
「ったく、危ねーなー。大丈夫か?」
転びかけた私の体を支えてくれたのは、浩市の腕だった。
思いがけなくすっぽりと、私は彼の腕の中におさまっていた。
思いがけなくすっぽりと、私は彼の腕の中におさまっていた。
「ごめんなさい、大丈夫だから…」
あまりに近い距離に動揺して、反射的に立ち上がろうとする。
「っ…!」
足に痛みが走る。
「無理するなって。」
「…ごめんなさい。時間、大丈夫ですか?」
申し訳ないのと恥ずかしいので、俯いたまま心にもない言葉を口にする。
「時間なんていいから。」
唇がそっと触れた。
驚いて顔を上げる。
浩市は「嫌だった?」とちょっとだけ笑った。
驚いて顔を上げる。
浩市は「嫌だった?」とちょっとだけ笑った。
「…嫌じゃない。」
「嫌じゃないなら、よかった。」
棒立ちになった私の腰を抱き寄せると、浩市はじっと目を覗き込んだ。
「嫌じゃないんだろ?(ニヤリ」
答える前に唇がふさがれた。
さっきよりもっと熱くて深いキス。
唇が離れる。名残惜しげにまた軽く重なる。
息継ぎをする間もなく、舌が差し込まれる。
息も心臓も止まりそう。胸が苦しい。
さっきよりもっと熱くて深いキス。
唇が離れる。名残惜しげにまた軽く重なる。
息継ぎをする間もなく、舌が差し込まれる。
息も心臓も止まりそう。胸が苦しい。
やっと離れた唇が、滑らかに耳元に移動した。
熱い舌が小さなピアスに触れる。
熱い舌が小さなピアスに触れる。
「飴、舐めてるみたいだな。」
浴衣越しに浩市の体温が伝わって来る事に気づいて、今更ながら緊張してしまう。
というか、この状況はとてもまずいんじゃないだろうか。
何がまずいのかよくわからないけど、とにかくまずい気がする。
私の体が硬直したがわかったのか、浩市は少し体を離した。
というか、この状況はとてもまずいんじゃないだろうか。
何がまずいのかよくわからないけど、とにかくまずい気がする。
私の体が硬直したがわかったのか、浩市は少し体を離した。
「どうした?」
「なんでも…。」
「嫌なの?」
この世にこの男を本気で拒絶できる女がいるなら、それはきっと女じゃない。
「…嫌じゃない、でも…。」
「でも?」
クリームソーダのアイスを舐めるように、浩市は私の首筋をひと舐めした。
男は女の話を聞かないというけれど、それはこの人にも当てはまるようだ。
首筋から、少しはだけてしまった胸元まで唇が往復する。
男は女の話を聞かないというけれど、それはこの人にも当てはまるようだ。
首筋から、少しはだけてしまった胸元まで唇が往復する。
「お母さん、着付け下手すぎ…。」
気をそらす為にどうでもいいことを考えていると、首筋に軽く歯を立てられた。
「っ…。」
必死でこらえていた声が漏れる。
私を抱きしめると、浩市が耳元で囁いた。
私を抱きしめると、浩市が耳元で囁いた。
「その声が、聞きたかった。」
あまりの恥ずかしさにかっとなって、思わず突き飛ばしてしまった。
「もう!時間大丈夫なん!?明日も仕事やないん!?
それやにこんなとこまで来て!私のことからかって!
…何が面白いんか、全然わからんわ。」
それやにこんなとこまで来て!私のことからかって!
…何が面白いんか、全然わからんわ。」
一気にまくし立てて座り込む。
こんな事を言いたいわけじゃなかったのに、一旦口から出てしまった言葉はもう戻らない。
「参ったな。」と言いたげな表情で空を仰いでいた浩市が、私を覗きこんで軽く頭をなでた。
こんな事を言いたいわけじゃなかったのに、一旦口から出てしまった言葉はもう戻らない。
「参ったな。」と言いたげな表情で空を仰いでいた浩市が、私を覗きこんで軽く頭をなでた。
「ごめんな。」
謝ってなんかほしくないのに。
*******************
浩市に助けられて、ようやく立ち上がる。
はだけた胸元を浩市が直してくれた。
はだけた胸元を浩市が直してくれた。
「…きもの、わかるの?」
「時代劇にも出ますからね。」
恥ずかしくて、下を向いたまま動けない。
「ほら。」
顔を上げると、浩市が手を差し出してくれていた。
その手にひかれて、ようやく歩き出す。前を向いたまま浩市がつぶやいた。
その手にひかれて、ようやく歩き出す。前を向いたまま浩市がつぶやいた。
「方言ってのもいいもんだな。」
「…ごめんなさい。」
「謝ることないだろ。」
「だって…。」
「足、大丈夫か?辛くなったら言えよ、おんぶしてやるからw」
なんでこの人は、せっかくの休みにこんな所まで来たんだろう。
場慣れしてない子供相手に、疲れが増したんじゃないだろうか。
私がもっと大人だったら、もう少し何か違ったんじゃないだろうか。
場慣れしてない子供相手に、疲れが増したんじゃないだろうか。
私がもっと大人だったら、もう少し何か違ったんじゃないだろうか。
「時間はあるんだ。」
「え?」
「こっちに宿取った。」
「しごとは?」
「仕事仕事って、お前は俺のマネージャーか。」
大通りでタクシーを停めると、浩市は黙ったまま乗り込んだ。
私は手をひかれたまま、どうしていいのかわからずにタクシーの脇に立ちつくす。
狭い後部座席から、浩市が私を見上げた。
私は手をひかれたまま、どうしていいのかわからずにタクシーの脇に立ちつくす。
狭い後部座席から、浩市が私を見上げた。
「…どうする?」